あらすじ一覧

(オープニングタイトル)
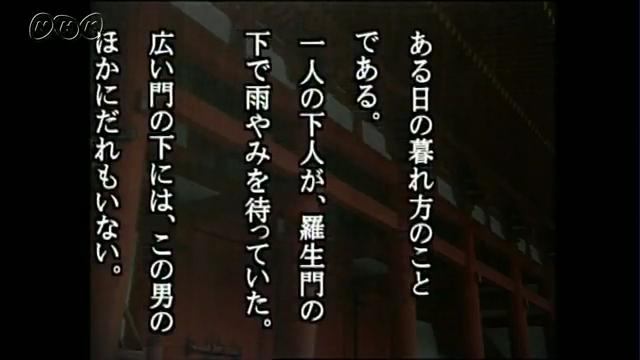
「ある日の暮れ方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下には、この男のほかにだれもいない。ただ、所々丹塗りのはげた、大きな円柱に、きりぎりすが一匹とまっている。羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみをする市女笠や揉烏帽子が、もう二、三人はありそうなものである。それが、この男のほかにはだれもいない。」

平安時代の京都。地震や火事、飢饉などさまざまな災いが度重なり、都は混乱と不安のなかにありました。物語の舞台である羅生門は、そんな都のはずれにあり、辺りは荒れ果て、引き取り手のない死体が捨てられる場所でした。その門の下で一人途方にくれていたのが、主人公である下人です。長年仕えていた主人から隙(ひま)を出され、仕事のあても行き場もありません。このまま餓え死にするか、盗人(ぬすびと)になるか、顔にできたにきびをつぶしながら考え続けていました。

「雨は、羅生門を包んで、遠くから、ざあっという音を集めてくる。どうにもならないことを、どうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、築地(ついじ)の下か、道端の土の上で、餓え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば――。下人の考えは、何度も同じ道を低回したあげくに、やっとこの局所へ逢着(ほうちゃく)した。」

『羅生門』を書いたのは、大正時代を代表する作家、芥川龍之介です。文壇に華々しく登場する直前、23歳のときの作品です。芥川は、この作品でさまざまな技巧を凝らして、ゆれ動く人間の心の危うさを丹念に描き出しています。その技巧の一つが、古典文学に題材をとることです。芥川が選んだのは、愛読していた『今昔物語集』でした。当時の都、平安京を南北に貫く大通り、朱雀大路(すざくおおじ)。その南端に建つ二階建ての大きな建物。これが、羅生門です。

今夜はここで明かそうと二階に上がった下人は、捨てられたいくつもの死体のなかにうずくまる一人の老婆を見つけて驚きます。老婆は女の死体から一本ずつ髪の毛を抜き始めます。「その髪の毛が、一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が、少しずつ動いてきた。――いや、この老婆に対すると言っては、語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。」

下人は、逃げる老婆を力ずくでねじ倒し、何をしていたのかと問いただします。「かつらにしようと思うたのじゃ」。老婆の平凡な答えに、下人は失望します。さらに、餓え死にしないためには悪いことも許される、という老婆の言葉が、下人の心を強くゆさぶりました。

ゆれ動く下人の心を描くためのさまざまな工夫の一つが、作者と名のる語り手と主人公との距離感です。下人が老婆に激怒する場面。「下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった」。下人の心をつぶさに観察し、分析する語り手。しかし、直後に続く文章では、急に突き放します。「もちろん、下人は、さっきまで、自分が、盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れているのである」。
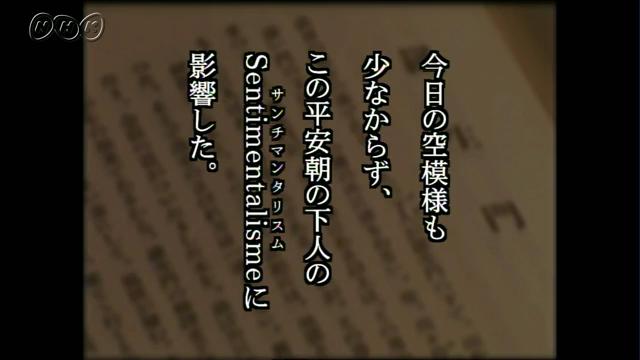
場面に応じて視点を変えていく語り手。それを象徴する表現があります。「今日の空模様も少なからず、この平安朝の下人のSentimentalisme(サンチマンタリスム)に影響した」。平安時代に生きる下人を、フランス語で表現する意外性。ここでは、語り手は時代も文化も超えたところから下人の姿をながめます。こうした、大胆かつ繊細に計算された語りが、この物語をはじめ、多くの芥川作品に共通する魅力となっています。

芥川は、物語の最後をどんな語りで締めくくるのでしょうか。老婆の言いわけを聞くうちに、下人の中で何かがくずれおち、悪へと踏み出す決意が固まります。下人は老婆から着物をはぎ取り、死骸(しがい)の上へ蹴り倒して走り去ります。

「しばらく、死んだように倒れていた老婆が、死骸の中から、その裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆は、つぶやくような、うめくような声をたてながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで、はっていった。そうして、そこから、短い白髪を逆さまにして、門の下をのぞき込んだ。外には、ただ、黒洞々たる夜があるばかりである。下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあった」。

下人が強盗を働くため都に急ぐ場面で物語は終わります。しかし三年後、芥川は最後の文章を全面的に書き直しました。「…そこから、短い白髪を逆さまにして、門の下をのぞき込んだ。外には、ただ、黒洞々たる夜があるばかりである。下人の行方は、誰も知らない」。